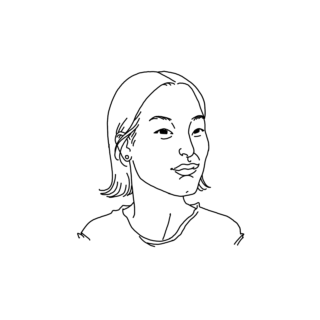FILM DIARY April 2023
暇さえあれば映画が見たいスプーン四年生による、
映画評論ブログ#8です。
よろしければお付き合いください。
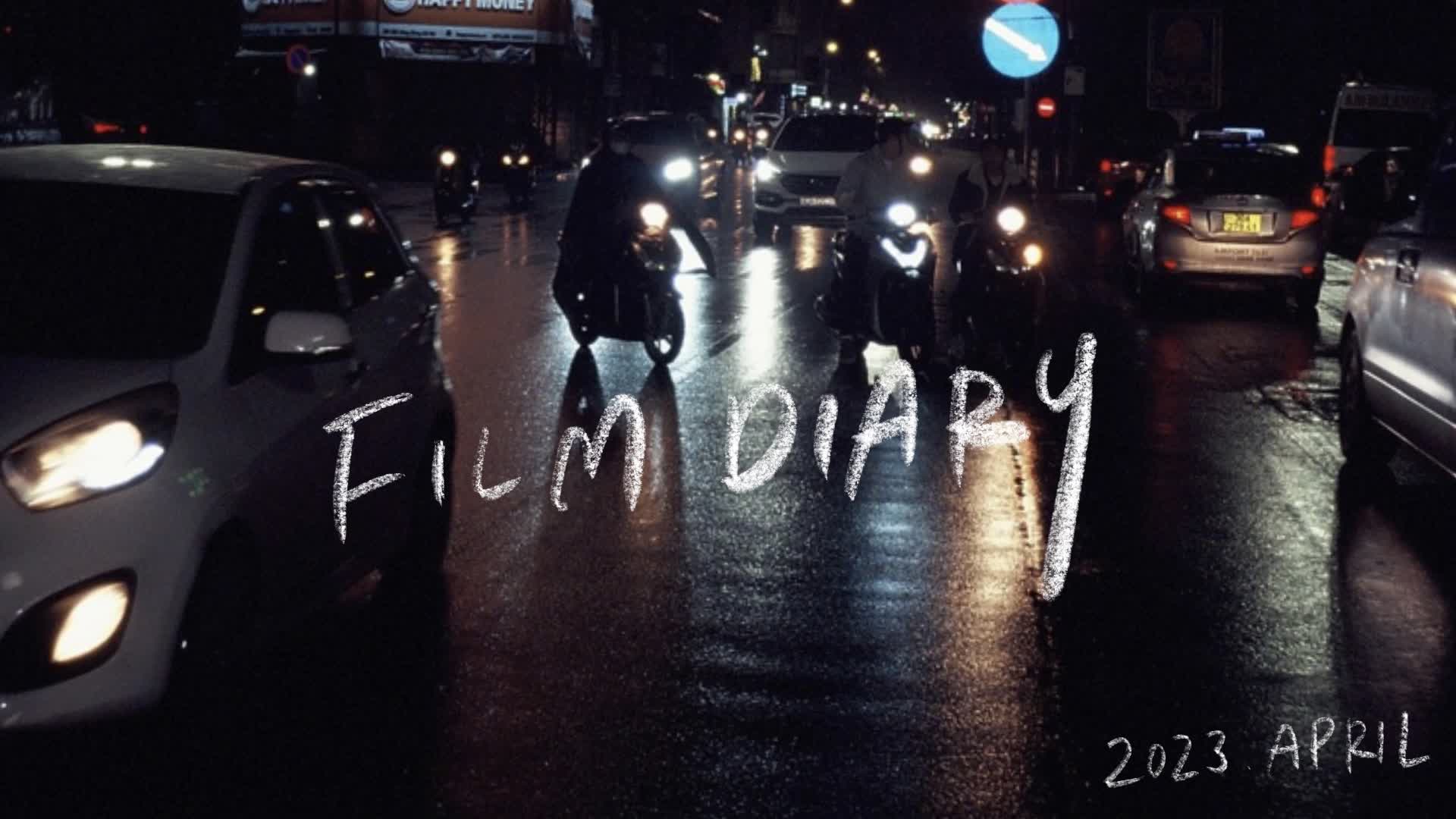
空間、場所、逃げ場について
自分が大学生の頃は、喉から手が出るほど見たくても見れない作品がたくさんあったが、(その頃は家の近くのツタヤに通って端から端までチェックして毎週なにかしらをレンタルするのが日課だった)大学院に入学したら、付属の資料室に入ると、宝の山のように自分が今まで観たくても上映もレンタルもされてなかったDVDやVHSが多くあって、本当に感動したのはいまでも覚えている。そこからさらに数年経っていまでは多くのこれまで観れなかったような作品が、特集上映が組まれたり、配信がスタートしているのはとてもありがたいしすごいことだなとよく思う。4/6から始まったシャンタル・アケルマン特集もそのなかのひとつだ。今回は彼女の作品の中で⼀際騒がしい『ゴールデン・エイティーズ』(1986)について。
上映後のトークショーでの坂本安美さんも同じようなことを言っていたが、本作で私が思ったのは映画における(とりわけ社会的弱者における)空間についてだ。年末に下高井戸シネマで観た『スチーム・バス女たちの夢』(1985)でも同じことを感じたのだが、まずは『ゴールデン・エイティーズ』のあらすじについて簡単に書くと、舞台は地下のショッピングモール。美容室があって、その前にはブティック、隣に小さなカフェがあって、少し進むと映画館がある。そのショッピングモールで働く老若男女の物語だが、話的には結構チープなもので、美容院の店長のおばさんに恋しちゃうブティックの若息子。そのおばさんはヤクザからお金をもらってその店を営業していることもあって、モールのみんなはその恋に対して批判的(あまりにも不釣り合い)。ブティックの息子を心配する両親は美容院のバイトの若い子と結婚しなさいと勧め、初め乗り気じゃなかった息子もまあまあ流されてそのバイトと婚約。
しかし、おばさんは若息子をたぶらかしているようで実は結構好きだったことが終盤に発覚。結果的にはそのおばさんがまた現れて(⼀瞬きえる!)、若息子と愛を確かめ合い、モールという空間から消えていく。ラストの終わり方があっけなくてなんだこの話は、と思うが、イントロから最後までミュージカルでコミカルな展開で話は進んでいく。
あらすじはひとまず、私が驚いたのはこの物語の舞台がその地下のモールだけで完結していることだ。やられたなと思ったのは最後の最後にやっと地上に登って、地上の街並みが映される(ほんの数分のみ)。狭い空間でも90 分の映画は容易に作ることができる。これを観て思い出したのが先に出した『スチーム・バス』で、こちらの作品は熟女がサウナに通ってそこで自分はいかに抑圧されている(たとえばひとりは旦那に、もうひとりは仕事に、もうひとりはもうわけわかんなくなっている)話で、これも舞台はサウナというかその健康ランド的な空間のみで外の世界は⼀切映されずに完結する。それでも物語には深みがあり、広がりがある。そしてこうやって書いてて再確認したが、この2作品は公開が1年しか変わらないのも面白い。時としてそうした閉鎖的空間は、抑圧の場所になるし、あるいは避難所ともなる。『スチーム・バス』の場合は健康ランドという空間は、逆に外の世界で抑圧されている女性たちにとってシェルターとしての役目を果たしている。そして『ゴールデン・エイティーズ』での地下のショッピングモールはある意味で避難所とも言えるが、そもそもの人間が営む場所(なぜならそこでは常に商売が行われ、出会いも別れも繰り広げられる)となる。 面白いなと思うのはそこでは争いが起きてもコミカルで、誰も誰かのことを悪くは言わない(そんな尻軽なおばさんのことも、バカそうな若息子のことも)。ある意味でユートピア。なんでこんな狂ったことができるんだと不安になるが、ただ、劇中で一言、ブティックを営む母親がそのブティックにたまたま訪れた昔の恋人に会った際に言うセリフでなんとなく監督のアケルマンの思想がわかるカットがある。
昔の恋人との会話のシーン、「彼女は当時本当に元気がなかった。つい収容所のことを思い出してしまう、元気になるまで見守っていた。」 だいたいこんなことを言うのだが、つまり母は当時収容所にいたことがわかる。そうしたただ一言のセリフでも閉鎖的空間=ネガティブな要素をいれるのは、そうした空間が時として抑圧的な空間になることを示唆している。そして実際にも、シャンタルの祖母は当時収容所に⼊っていた経験があるのだという。孫である彼女はその話を具体的に聞くことはなかったが、残された日記を(ほとんど破られていたらしい)読み、その事実は把握している。単純に考えたら閉鎖的空間に対してネガティブな思いを持っているはずのそんな彼女が、地下(しかも地下…となる)の外部の光が見えないような空間であそこまで明るく喜劇を描けるのは本当にすごいことだと思った。自分、もしくは近しい人間の経験をネガティブに描くこともできるが、こうやって新しい物語を紡ぎ出すそのセンスにただ憧れる。
◇
大学院ではアッバス・キアロスタミの研究をしていました。たまに批評誌サイトに寄稿したりしています。見た映画のなかから考えたことなどをこれから少しずつ書いていこうと思います。
2023/04/20